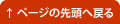議題21号 稲作農家の経営の安定を求める意見書(案)の賛成討論
2014.10.10
意見書案への賛成討論をしました。
討論は以下のとおりです。
議題21号 稲作農家の経営の安定を求める意見書(案)の賛成討論
日本列島各地で自然災害に見舞われながら、ようやく実りの秋を迎えました。豊作を喜ぶ穫り入れの秋です。しかし、今年は米価暴落で長野県産コシヒカリの概算金は昨年を15%下回り60キロ1万192円。あきたこまちは8812円で1万円を下回り、過去10年で最低となりました。
農水省の調査でしめされている稲作農家が他産業並みの労賃を得て米作りをするには、平均で玄米60キロ1万6000円が必要とされています。さらに現状は消費税増税と円安による物価高で生産コストと生産者米価の溝は開くばかりと言わざるを得ません。
実りの秋を喜ぶどころか、米作ってメシ喰えない状況です。
今年の米価暴落の背景には、JA全農(全国農協連合会)や米卸売業者が13年産米の在庫を過剰に抱え、「投げ売り」する状況と、作況がよく供給量が需要量を大幅に上回る見通しになったことがあるといわれています。これに対して、政府は稲作農家の収入減少に対する補てん制度として、認定農業者等を加入者とする収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)等で対処するとしているが、この対策では根本的な対策にはなりません。
安倍内閣は、輸入米を増やす環太平洋連携協定(TPP)を前提に、国の需給調整責任を放棄し、2018年産から国による米の生産調整を廃止することになっており、生産調整を達成した農家への交付金も今年から半減という状況です。全国のコメ産地では、経営の見通しが立たないと離農が進んでいます。政府の責任によって米価対策が行われず、市場任せで米価暴落が放置されれば、地域の営農維持や農村集落にも深刻な影響をもたらしかねません。それは、生産者への影響にとどまらず、わが国の食料自給率の一層の低下を招くことになります。
政府として、過剰米の市場隔離をはじめ、コメの需給調整を直ちに行うこと。さらに抜本的な経営安定対策を講じることを求めて賛成討論とします。
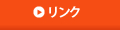

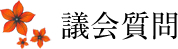 議会質問
議会質問