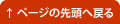一般質問
2014.10.06
生活保護と生活困窮者自立支援、そして知事が制定を目指している淫行処罰条例について質問しました。
1、生活保護について
昨年8月の生活保護基準の切り下げによる影響について、昨年9月議会では「生活保護世帯の8割が減額という影響をうける」ことや、「世帯構成や居住地域などで多少異なるが、30代のご夫婦と4歳の子ども1人という世帯を例に郡部では2,500円程度、市部では4,800円程度の減額」との答弁でした。
生活扶助基準の切り下げ以前に、母子加算や老齢加算が廃止され、生活保護世帯の生活はギリギリのところに更なる引き下げによって生活実態はどうなっているか、福祉事務所が生活保護受給者を定期的に訪問調査をして、状況をどうとらえ、実態を把握しているのか健康福祉部長に伺います。
長野県民主医療連合会が、今年1月から3月に生活保護受給者224人に聞き取り調査をした結果。1日の食事回数「1回」「2回」が76人。3回の食事ができない人が3割。1週間の入浴回数「3回以下」が75%にものぼっていました。
保護費での生活はギリギリでこれ以上削れない、しかたなく食事を1回減らす、これが日常的になることを想像できますか。
1日の食事3回でも内容は、ある方は、朝はご飯と卵豆腐と味噌汁。昼はごはんと佃煮。夕飯はカップラーメン。また、ある方は、朝はパン。昼は33円のうどん。夜は88円のレトルトカレー。体にいいわけないけどそうするしかない。何人もの方が節約のため、ガスは止めた。夏は日が長いから電気止める。着るものは何年も買っていない。親族やご近所も付き合うお金がないから一切断ち切った。本当に深刻な実態です。
今年4月から、消費税8%増税と円安で、水光熱費、食料品はじめ生活必需品の値上げラッシュは、厳しい生活に拍車をかけるばかりです。県として生活保護受給者世帯の深刻な実態を把握して、国に対して生活保護基準の見直しを求めるべきではありませんか。更なる引き下げはやめるよう求めてべきです。健康福祉部長に伺います。
条件付きで、車の保有、住宅など資産があっても生活保護の申請・受給ができる、厚労省の通達の適正な運用を行うよう、改めて県として繰り返し徹底してほしいがいかがですか。
また、車の保有によって生じる経費についても生活保護費に加算されるよう国に求めるべきと考えます。健康福祉部長に伺います。
下諏訪町では今年冬の灯油の値上がりと厳しい寒さに対して「福祉灯油券」を検討したが実現できず。低所得世帯、生活保護世帯には「福祉灯油券」にかえて、下諏訪町内で使える「生活応援商品券」の配布を行おうとしました。この商品券の配布に当たり、下諏訪町が福祉事務所に相談したところ、諏訪福祉事務所長名で6月19日付「下諏訪町が配布する商品券の扱いについて」という通知を出し、平成26年4月の保護基準の改定により消費税率の引き上げによる負担増への対応が既に行われているため、商品券は収入認定する。
商品券5000円分については、受領した場合には7月から11月までの5カ月間、分割して毎月1000円の収入認定を行い、生活保護費を1000円減額する。配布された商品券は必ず受け取り、7月中に収入認定申告書を提出すること。さらにダメを押すように、「商品券を受け取らない場合、収入申告を行わない場合、保護の変更をする。」と記載があり、受給者の方は保護の打ち切りになるかと心配して共産党に相談がありました。
結局、下諏訪町は福祉目的で商品券を配ろうとしたことが、消費税対策と福祉事務所に受け取られ、これが収入認定、保護費の減額の扱いといわれたため商品券は断念しました。
この下諏訪町の事例について、諏訪福祉事務所から本庁担当課に相談されて、あくまで消費税対策で「経済支援目的である」という指導をしたわけです。
自治体の福祉目的でという意向を尊重してできるだけ実施できるように県はサポートすべきではなかったのか、健康福祉部長に伺います。
問題はその後にもおきました。実際には商品券が配られなかったにもかかわらず、福祉事務所は商品券が配られたと思いこみ7月分の保護費を1000円減額しました。この事実に気付いて諏訪福祉事務所が出した通知は、翌月の保護費を増額するという一遍のもので、謝罪の言葉もなく、7月中に返還もしようとはしなかった。収入申請がないのに、勝手に収入を見込んで保護費を減額支給しておきながら、翌月「増額」とはあまりにひどい話です。
1000円減額は死活問題です。気が付いた時点ですぐに謝罪して、返すのが当然のことです。この一連の事実に対して、県として改めて下諏訪町と受給者に対して謝罪すべきではないですか。健康福祉部長に答弁を求めます。
下諏訪町は商品券を、高齢者、母子・父子家庭、生活困窮者には配りました。けれど、青木町長は思わぬ事態になり一番受け取って欲しかった「生活保護世帯には町の施策が届かなかった」と言われたそうです。今回の商品券は福祉灯油と同様の扱いで8000円までは収入認定除外規定が当てはまるケースとして、健康福祉部は生活保護世帯を応援しようとした下諏訪町の真意を汲んで対応すべきだったのではないですか。
国は、保護基準の切り下げにとどまらず、いわゆる「改正」生活保護法が施行され、生活保護の利用の抑制が強まるのではないかと危惧を抱いています。生活保護は最後のセーフティネットです。心ある生活保護行政に努めてください。
2、生活困窮者自立支援事業についてうかがいます。
4月からパーソナルサポートセンターを4か所から6か所に増やし、委託先を労福協から社協に変えたのは、来年度から生活困窮者自立支援事業に移行していく過程でのことと思われます。その際に、委託先を変えても相談支援員の雇用の継続や、年度当初の事業を引き継では相談支援に空白期間が生じないよう体制を整えて欲しいと繰り返し要望してきました。知事も、PS事業による寄り添い型支援の要は相談支援員という認識を持ち、相談支援員の雇用継続を担当課に求めると公言しました。にもかかわらず、事業の委託先が変更になることで雇用が継続できないのはやむを得ないと手のひらを返す結果でした。雇用の継続の約束は守られず、裏切られた思いです。今後、生活困窮者自立支援事業に移行するにあたり、県の責任を後退させることなく、今以上に自立支援の関係事業に本気で取り組んでほしいと思います。知事の決意をお伺いします。
また、4月当初から事実上相談事業が中断したセンターがあったことも含め、県の対応が現場を混乱させたと指摘をせざるを得ません。委託先が変わって半年経過しましたが、これまでの相談者への相談支援の引継ぎ状況はどうなっているか。又、新たな相談者への支援状況はどうなっているか健康福祉部長にお聞きします。
派遣や期間工など人を調整弁にして、企業のもうけのために人をモノのように使い捨てにする、就労しても不安定、低賃金、企業は十分な研修を保障しない。仕事を失えば住むところも失う。年収200万円以下の働く貧困層1100万人のうち年収100万円以下の労働者は421万人にも上ります。劣悪な労働環境によって、PSの相談者は人格を傷つけられ、すぐに就労につなげられない方が多く、相談支援だけでは不十分です。ところが、国は生活困窮者自立支援事業のうち、相談支援事業は必須事業とするが、就労準備支援事業、家計相談事業、学習支援事業、一時生活支援事業は任意事業で必須事業の扱いになっていませんが、どの事業も必要です。県はどう認識しているのでしょうか。
任意事業の中から実施する事業は自治体が選択するということでは、自治体ごとで格差を生んでしまいます。自治体ごとの特性・独自性などと矮小化することなくすべて必須事業とするよう国に要望すべきではないかと考えます。
また、今回の委託先変更でも、相談支援員の身分が保証されず、相談を受ける側の雇用まで不安定だということが明らかになりました。自立相談事業を担う相談支援員の養成と身分保障が必要です。正規職員として人件費を保障することを国に求めるべきではないかと考えます。健康福祉部長に伺います。
県がパーソナルサポート事業と絆再生事業を拡充してきたことは、とても大事なことです。先ほど就労準備支援事業、家計相談事業、学習支援事業、一時生活支援事業を必須事業に位置付けるよう求めましたが、県はすでに絆再生事業として、民間支援団体が取り組む活動を応援してきました。絆再生事業は県下10カ所で、年間を通して相談会や支援物資の配布活動。年末きずなむらの活動、子どもたちへの無料学習支援活動をしています。さらに長野では里庵という居場所ができ、毎月延べ200名を超える利用者があります。遊休地でコメ作りに挑戦するなど多面的な活動に発展しています。無料塾もサポーターの協力で毎月継続しています。絆再生事業によって大きな絆ができてきました。その中で、引きこもっていた人が就労の面接に行けるようになりました。絆再生事業は有機的な事業になっています。来年度以降も継続していくべきだと思います。健康福祉部長にお聞きします。
県としてはパーソナルサポート事業を、平成27年度には実施主体が福祉事務所設置自治体に設置義務になるため、県および19市で実施するということになるわけですが、19市で均等なサービス提供は容易にはできないと思います。今後、事業における県の役割をどう考えているのか伺います。
寄り添い型のPS事業でしっかりサポートして自立につなげていくには、NPO、民間支援団体、企業や行政などの協力が必要という認識で、県は連絡会をひらいているわけですが、今後県と19市へ移行していくにあたっては、いままでの連絡会を核に広域的なネットワークの構築が必要になると考えます。県が責任を持ってネットワークを構築して、コーディネートは県が担っていくべきはないでしょうか。そのために県は人的な配置をすべきと考えます。健康福祉部長にお伺いします。
3、子どもを性被害から守るための県の取組みについて
知事にあてて「子どもを性被害等から守る専門委員会」や県青少年育成県民会議から検討した結果の報告書が提出されました。これを受けて知事は条例制定の検討も含めて9月25日に「子どもを性被害から守るための県の取組み(案)」を公表しました。このなかで、予防・被害者支援・県民運動の再活性化の3つの取組みを早急に実施するとしています。
子どもの性被害は、大人社会のモラル、特に、こどもを性の対象にする、商品化するという点で日本が欧米各国と比べ異常な環境だという認識を持って、早急に県民参加で3つの取組みを実施してほしいと思います。
まず、学校での性教育は、小学校から発達段階にあった性教育をするため、教育委員会が独自のテキストを作成したということですが、その中でいのちの大切さを教え、こどもたちは自分を大事にすることを学んでいると思いますが性教育の具体的な充実について教育長に伺います。
県内には退職後の養護教諭のみなさんが「まちの保健室」を開いて、様々な相談を受けてくださっています。深刻な性被害に至る前に身近に相談できるところとして、地域でがんばっておられます。また、長野県はこれまでも県民運動で頑張ってきました。これを再構築し充実、活性化させていけばよいのではないでしょうか。
淫行処罰条例でなければ対応できない事例というのはどういうものなのか。厳罰化で果たして被害がなくなるのか、現行法でも性犯罪を取り締まり、逮捕や処罰ができるにもかかわらず、処罰規定を盛り込む県条例の必要性はないのではないかと思います。知事に伺います
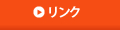

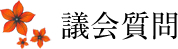 議会質問
議会質問