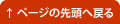一般質問要旨
2014.06.25
2014年6月24日和田議員一般質問要旨
1【農業に関連して】
TPP交渉について、オバマ大統領は11月大筋合意し、年内に妥結という日程に言及し、あからさまに日本政府に妥協を迫っており、安倍総理は、TPPは「確固たる日本の進路だ」「TPPに大きな期待を託している」と早期妥結へ決意を示すなかで、日本政府としては、来月上旬の首席交渉官会合で早期妥結に向けた道筋をつけるためには、難航する農産物の関税交渉を決着に近付ける必要があるとしており、首席交渉官会合を前に、アメリカなど各国との間で2国間協議を加速させています。政府が「聖域」とした農産物重要5品目の関税引き下げなど譲歩に譲歩を重ねていることは明らかです。
豚肉は差額関税の大幅削減で、現在1キロ当たり最大482円の関税を15年かけて50円に下げることや、牛肉は38.5%の関税を10年かけて9%にする。米、麦、乳製品については、関税を維持する代わりに特別な輸入枠を拡大する等の報道がされて、畜産農家からは「交渉すればするほど譲歩することになる。もう交渉をやめてくれ」とTPP交渉からの脱退を望む悲鳴のような声が上がっています。
政府が重要5品目は「聖域」として関税撤廃の例外にするといった前提が崩れたことに対して危機感を持って対処をすべきと思います。まず、長野県農業への影響について、県として、重要5品目を含めた農業生産額への影響額の試算をしていると思う。2013年の5月の時点ではその公表を保留していたが、その試算結果を農政部長にお聞きします。
昨年5月時点では公表する試算はしていなかったということであるが、これだけ交渉が進んでいる中で、未だに試算をしていないということはどういうことかと本当に驚くばかりの答弁であります。
昨年4月の国会は米等の重要5品目を関税撤廃の対象からはずすことや、それが確保できないと判断した場合は交渉からの脱退の国会決議をしています。また、県議会においても昨年9月議会で、TPP交渉によって国益を損なうことが明らかとなった場合は、即刻、交渉から脱退すること。を明記した意見書を全会一致で可決しています。政府が「聖域」として関税撤廃の例外にするといった重要品目についても関税撤廃は避けられない状況で、その影響が甚大であることを知事はどう考えるのか、また、試算していないと言う長野県の農政のあり方についてもどう思うのか、国に対してはっきりとTPPからの撤退するよう意見をあげるべきではないか。知事におうかがいします。
TPP交渉がこのまま進められていけばどういう影響が及ぶのかについては、県農政部としても影響を試算すべきではないかということを、改めてもう一度農政部長にお伺いしたいと思います。また、安倍晋三内閣の「農政改革」はTPP交渉の早期妥結を前提に、コメの生産調整の廃止、米直接支払助成金の削減・廃止、農業への企業参入の自由化などを推し進めようとしています。そして、規制改革会議からは、「農業改革に関する意見書」として農業委員会制度の見直し、JA中央会の廃止など、農業・農政に関わる規制や関連組織の大幅な改変が出された。農業委員会制度のあり方やJAの解体の議論といった農業関係の動きは、TPP妥結に向けての地ならしではないですか。知事の見解をお聞きします。
農政部長の答弁には、本当に私はがっかりしました。危機感を持ってしっかりと取り組んでいただきたいということを言わせていただきます。
また、長野県特有の、耕作地の集積ができない中山間地での農業は、いずれも家族農業とその共同を基本にした農業です。その結果、長野県は農家戸数日本一です。この長野県の農業を、今回の農政改革は、根本から覆す問題です。その実情をしっかりとらえて地方から声をあげることが大事ではないでしょうか。農業県の長野県の知事として、国益を損なうことが明らかであるこのTPP交渉について、現場の声を踏まえて意見をあげて欲しいと要望しておきます。
2【長野県の未来を担う子どもの支援に関する条例について】
条例要綱案を示して、幅広い観点からの議論を経て、条例案を県議会に提出したと知事はいわれますが、条例案は議会直前の6月13日にようやく示されたところです。やはり重要な条例を制定するのですから条例案を県民にしめし、広い県民参加の意見聴取や議論を求めるべきではないかと考えます。
知事の任期中に条例制定をする気であれば、どうしてもっと早くから条例案を出さなかったのですか。知事は条例を議会が通してくれればいいと安易に考えているのですか。
第一に、県が制定する条例ですが、「子ども支援は、国、市町村、保護者、学校関係者等、事業者、県民等が各々の役割を果たすことにより重層的に行うとともに、相互に連携協力して継続的におこなわなければならない。」と基本理念に明記されているように、県の関係機関や議会だけの議論、意見集約、周知に留めるものではありません。
条例が実効あるものになるような取り組みがされたのですか、関係者に理解と協力を呼びかけられたのか県民文化部長にお聞きします。今後どのように周知し理解と協力を得ていくのかについてもお聞きします。
いま部長は条例が可決されてからと言いましたけれども、これは大変大事なことであり、条例が今の条例案のときに、こういうことを皆さんにお知らせして、協力を得ていくという努力をしてから条例を提案すべきではないかと思います。
4年前の知事選挙において阿部知事が子どもの権利条例の制定を公約に掲げていたことに対して、多くの県民は期待をしました。
子どもの権利条例の制定を前提にして「子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会」においてご尽力された方々からは、子どもを権利の主体として条例を制定するよう求められており、知事も条例に想いがあるのではないですか。
松本市の菅谷市長は、松本市の子どもの権利条例を検討する際に、「そもそも大人が子ども達を育てるという、大人の側からの「子どもを保護すればよい」という発想に固執しがちであるが、それでは子どもの成長を抑制してしまうと発言し、「子育てはできても、子育ちにはならないので、子ども自身が主体的に生きるために、自分の考えを適切に表現する子どもの権利主体としての子ども観」を求めたという経過があると聞いています。これについて、知事はどうお考えかお伺いします。
松本市の条例では「子どもにとって大切な権利」を明らかにした上で、子どもの育ちへの支援や子どもを支援する者への支援を定めています。知事の公約は「子どもの権利」条例の制定であったはずであり、目指したのは松本市のような条例ではなかったのかについてもお聞きします。
選挙公約では「子どもの権利条例」といわれていたと思うんですけれど、知事には確固とした理念がなかったということではないかということを、肝心なところをはぐらかされているような思いを今の答弁でも感じています。
要綱案から条例案へと、共通しているのは、子どもが権利の主体としたとらえかたでなく、子どもを保護の対象ととらえているのではないでしょうか。
要綱案に対する意見を反映し何点か修正がされたといいますが、要綱案からの変更部分は、①子どもの育成には権利の尊重だけでなく、社会規範の順守や自制心を身につけさせることも大切だ。②子育ての基本は家庭であり、家庭教育への支援を盛り込むべきだ。という2月議会で指摘された点が、そのまま盛り込まれているのではないでしょうか。
要綱案からの変更部分も含め意見が分かれるところであります。条例案としての意見聴取の機会を全く持たないまま、このまま条例制定へというのは早すぎると私は思います。この点知事いかがお考えでしょうか。
知事も県民の声に耳を傾けてもらいたいと申しておきます。今議会で即決と言うことではなくやはりもっと広く意見集約をする機会を持っていただきたいということを要望しておきます。
3【パーソナルサポート事業について】
長野県が2011年度から実施している、パーソナルサポートモデル事業が今年度から、県と市町村との共同事業として、相談支援拠点も4か所から6か所に増えることに伴い、事業の委託先が変更されました。
その際、寄り添い型の生活困窮者支援として取り組んできたパーソナルサポート事業の成果と経験が良い形で引き継がれるよう、質問でも繰り返し取り上げてきましたし、生活困窮者支援の活動をしている市民団体の皆さんと担当部局との懇談、要望もしてきました。そのなかで、単に相談者の情報を引き継ぎ、支援すればよいということではなく、相談者ひとりひとりに支援員がマンツーマンで寄り添うという事業の本質を引き継ぐために相談支援員の雇用の継続が重要だという認識を県は持って対応していただけると考えていました。しかし現実には、残念ながら、新しい委託先に雇用が継続された方は一部にとどまりました。
地域によってはパーソナルサポートセンターの所長をハローワークで募集するなど、事業の継続性に疑問を持たざるを得ません。支援員の処遇が安定しないと、これまでの事業の継続性が担保される保障になりません。この点はどう考えておられるのか、健康福祉部長に伺います。
部長からは来年度の事業継続に向けての取組についても一部答弁がありました。このパーソナルサポートの事業は、大事なことは支援が必要な人は支援する人たちが離さないということだと思います。
パーソナルサポートの相談支援員として今度の委託先に雇用が継続されなかった人も、相談者の手を離すことはできないと言って頑張っている方もおられます。今までの事業の蓄積とネットワークをつくることを、県として責任を持って取組んでいただきたいと思いますので、再度部長に確認をしておきたいと思います。
知事は、提案説明の最後に、県政の課題と向き合い、一定の成果を挙げることができたことの一つに、困難を抱える人たちを支援するパーソナルサポートセンターの事業を言われました。
今年の2月県会前の知事への要望で、支援員の継続を求めた際に、知事からは継続の重要性を認識している旨の発言があった。今定例会の議案説明においても、パーソナルサポートの重要性を知事は実績として挙げているが、この継続が中身を持って帰属されているのか私たちは疑問を持っているが、実態は胸を張れる事業になっているのか。この事業についての知事の考えをお聞きします。
継続性を担保するということでは、今回疑問に感じざるを得ないものも実際にはある。問題点をしっかり把握して、来年度以降市町村事業に移行するが、県が責任を持ってこの事業が拡充・引き継がれていくよう取組んでいただきたいと要望しておきます。
4【生活保護基準の切り下げの問題や影響について】
いままでも質問をしてきましたので今日は、生活保護基準切り下げ(見直し)の影響が様々な制度の利用者に影響があるという問題で1点だけ質問します。
子どもの貧困が広がり、貧困の連鎖も深刻であります。子どもたちがお金の心配なく学校生活ができるよう、就学援助制度や高校生に対する県の奨学金制度があります。この制度も生活保護基準が一つの基準になっています。そこで、基準の引き下げの影響を受けないよう、対象世帯の年収が生保基準の1.5倍以下であるという要件の緩和をして、対象が狭められないようにすべきと思いますが、この点を教育長にお伺いします。
たしかに奨学金の貸付制度については、生活保護基準の1.5倍以下という基準のみをもってしてこの制度に当てはめるのではないということは承知しています。しかし、生活保護基準の切り下げられたもとでこの1.5倍という数字があったことによって対象にならなかったということが無いように、ここは全国的にも基準の1.5倍という数字についてもの緩和をしておりますので、ぜひここを改めていただきたいと思います。
そしてその基準によって、多くの制度に影響が及ぶということに対して、下村文部科学大臣も、生活保護費の引下げに伴い経済的に困窮している家庭が、制度の適用を受けられなくなるおそれが出ているというふうに言っている。そして自治体で必要な対策を講じる様に促すという考えを示しています。そこで県から国に対して、そういうことであれば対策に必要な予算も合わせて要望をしていただきたいと申して一切の質問を終わります。
1【農業に関連して】
TPP交渉について、オバマ大統領は11月大筋合意し、年内に妥結という日程に言及し、あからさまに日本政府に妥協を迫っており、安倍総理は、TPPは「確固たる日本の進路だ」「TPPに大きな期待を託している」と早期妥結へ決意を示すなかで、日本政府としては、来月上旬の首席交渉官会合で早期妥結に向けた道筋をつけるためには、難航する農産物の関税交渉を決着に近付ける必要があるとしており、首席交渉官会合を前に、アメリカなど各国との間で2国間協議を加速させています。政府が「聖域」とした農産物重要5品目の関税引き下げなど譲歩に譲歩を重ねていることは明らかです。
豚肉は差額関税の大幅削減で、現在1キロ当たり最大482円の関税を15年かけて50円に下げることや、牛肉は38.5%の関税を10年かけて9%にする。米、麦、乳製品については、関税を維持する代わりに特別な輸入枠を拡大する等の報道がされて、畜産農家からは「交渉すればするほど譲歩することになる。もう交渉をやめてくれ」とTPP交渉からの脱退を望む悲鳴のような声が上がっています。
政府が重要5品目は「聖域」として関税撤廃の例外にするといった前提が崩れたことに対して危機感を持って対処をすべきと思います。まず、長野県農業への影響について、県として、重要5品目を含めた農業生産額への影響額の試算をしていると思う。2013年の5月の時点ではその公表を保留していたが、その試算結果を農政部長にお聞きします。
昨年5月時点では公表する試算はしていなかったということであるが、これだけ交渉が進んでいる中で、未だに試算をしていないということはどういうことかと本当に驚くばかりの答弁であります。
昨年4月の国会は米等の重要5品目を関税撤廃の対象からはずすことや、それが確保できないと判断した場合は交渉からの脱退の国会決議をしています。また、県議会においても昨年9月議会で、TPP交渉によって国益を損なうことが明らかとなった場合は、即刻、交渉から脱退すること。を明記した意見書を全会一致で可決しています。政府が「聖域」として関税撤廃の例外にするといった重要品目についても関税撤廃は避けられない状況で、その影響が甚大であることを知事はどう考えるのか、また、試算していないと言う長野県の農政のあり方についてもどう思うのか、国に対してはっきりとTPPからの撤退するよう意見をあげるべきではないか。知事におうかがいします。
TPP交渉がこのまま進められていけばどういう影響が及ぶのかについては、県農政部としても影響を試算すべきではないかということを、改めてもう一度農政部長にお伺いしたいと思います。また、安倍晋三内閣の「農政改革」はTPP交渉の早期妥結を前提に、コメの生産調整の廃止、米直接支払助成金の削減・廃止、農業への企業参入の自由化などを推し進めようとしています。そして、規制改革会議からは、「農業改革に関する意見書」として農業委員会制度の見直し、JA中央会の廃止など、農業・農政に関わる規制や関連組織の大幅な改変が出された。農業委員会制度のあり方やJAの解体の議論といった農業関係の動きは、TPP妥結に向けての地ならしではないですか。知事の見解をお聞きします。
農政部長の答弁には、本当に私はがっかりしました。危機感を持ってしっかりと取り組んでいただきたいということを言わせていただきます。
また、長野県特有の、耕作地の集積ができない中山間地での農業は、いずれも家族農業とその共同を基本にした農業です。その結果、長野県は農家戸数日本一です。この長野県の農業を、今回の農政改革は、根本から覆す問題です。その実情をしっかりとらえて地方から声をあげることが大事ではないでしょうか。農業県の長野県の知事として、国益を損なうことが明らかであるこのTPP交渉について、現場の声を踏まえて意見をあげて欲しいと要望しておきます。
2【長野県の未来を担う子どもの支援に関する条例について】
条例要綱案を示して、幅広い観点からの議論を経て、条例案を県議会に提出したと知事はいわれますが、条例案は議会直前の6月13日にようやく示されたところです。やはり重要な条例を制定するのですから条例案を県民にしめし、広い県民参加の意見聴取や議論を求めるべきではないかと考えます。
知事の任期中に条例制定をする気であれば、どうしてもっと早くから条例案を出さなかったのですか。知事は条例を議会が通してくれればいいと安易に考えているのですか。
第一に、県が制定する条例ですが、「子ども支援は、国、市町村、保護者、学校関係者等、事業者、県民等が各々の役割を果たすことにより重層的に行うとともに、相互に連携協力して継続的におこなわなければならない。」と基本理念に明記されているように、県の関係機関や議会だけの議論、意見集約、周知に留めるものではありません。
条例が実効あるものになるような取り組みがされたのですか、関係者に理解と協力を呼びかけられたのか県民文化部長にお聞きします。今後どのように周知し理解と協力を得ていくのかについてもお聞きします。
いま部長は条例が可決されてからと言いましたけれども、これは大変大事なことであり、条例が今の条例案のときに、こういうことを皆さんにお知らせして、協力を得ていくという努力をしてから条例を提案すべきではないかと思います。
4年前の知事選挙において阿部知事が子どもの権利条例の制定を公約に掲げていたことに対して、多くの県民は期待をしました。
子どもの権利条例の制定を前提にして「子どもの育ちを支えるしくみを考える委員会」においてご尽力された方々からは、子どもを権利の主体として条例を制定するよう求められており、知事も条例に想いがあるのではないですか。
松本市の菅谷市長は、松本市の子どもの権利条例を検討する際に、「そもそも大人が子ども達を育てるという、大人の側からの「子どもを保護すればよい」という発想に固執しがちであるが、それでは子どもの成長を抑制してしまうと発言し、「子育てはできても、子育ちにはならないので、子ども自身が主体的に生きるために、自分の考えを適切に表現する子どもの権利主体としての子ども観」を求めたという経過があると聞いています。これについて、知事はどうお考えかお伺いします。
松本市の条例では「子どもにとって大切な権利」を明らかにした上で、子どもの育ちへの支援や子どもを支援する者への支援を定めています。知事の公約は「子どもの権利」条例の制定であったはずであり、目指したのは松本市のような条例ではなかったのかについてもお聞きします。
選挙公約では「子どもの権利条例」といわれていたと思うんですけれど、知事には確固とした理念がなかったということではないかということを、肝心なところをはぐらかされているような思いを今の答弁でも感じています。
要綱案から条例案へと、共通しているのは、子どもが権利の主体としたとらえかたでなく、子どもを保護の対象ととらえているのではないでしょうか。
要綱案に対する意見を反映し何点か修正がされたといいますが、要綱案からの変更部分は、①子どもの育成には権利の尊重だけでなく、社会規範の順守や自制心を身につけさせることも大切だ。②子育ての基本は家庭であり、家庭教育への支援を盛り込むべきだ。という2月議会で指摘された点が、そのまま盛り込まれているのではないでしょうか。
要綱案からの変更部分も含め意見が分かれるところであります。条例案としての意見聴取の機会を全く持たないまま、このまま条例制定へというのは早すぎると私は思います。この点知事いかがお考えでしょうか。
知事も県民の声に耳を傾けてもらいたいと申しておきます。今議会で即決と言うことではなくやはりもっと広く意見集約をする機会を持っていただきたいということを要望しておきます。
3【パーソナルサポート事業について】
長野県が2011年度から実施している、パーソナルサポートモデル事業が今年度から、県と市町村との共同事業として、相談支援拠点も4か所から6か所に増えることに伴い、事業の委託先が変更されました。
その際、寄り添い型の生活困窮者支援として取り組んできたパーソナルサポート事業の成果と経験が良い形で引き継がれるよう、質問でも繰り返し取り上げてきましたし、生活困窮者支援の活動をしている市民団体の皆さんと担当部局との懇談、要望もしてきました。そのなかで、単に相談者の情報を引き継ぎ、支援すればよいということではなく、相談者ひとりひとりに支援員がマンツーマンで寄り添うという事業の本質を引き継ぐために相談支援員の雇用の継続が重要だという認識を県は持って対応していただけると考えていました。しかし現実には、残念ながら、新しい委託先に雇用が継続された方は一部にとどまりました。
地域によってはパーソナルサポートセンターの所長をハローワークで募集するなど、事業の継続性に疑問を持たざるを得ません。支援員の処遇が安定しないと、これまでの事業の継続性が担保される保障になりません。この点はどう考えておられるのか、健康福祉部長に伺います。
部長からは来年度の事業継続に向けての取組についても一部答弁がありました。このパーソナルサポートの事業は、大事なことは支援が必要な人は支援する人たちが離さないということだと思います。
パーソナルサポートの相談支援員として今度の委託先に雇用が継続されなかった人も、相談者の手を離すことはできないと言って頑張っている方もおられます。今までの事業の蓄積とネットワークをつくることを、県として責任を持って取組んでいただきたいと思いますので、再度部長に確認をしておきたいと思います。
知事は、提案説明の最後に、県政の課題と向き合い、一定の成果を挙げることができたことの一つに、困難を抱える人たちを支援するパーソナルサポートセンターの事業を言われました。
今年の2月県会前の知事への要望で、支援員の継続を求めた際に、知事からは継続の重要性を認識している旨の発言があった。今定例会の議案説明においても、パーソナルサポートの重要性を知事は実績として挙げているが、この継続が中身を持って帰属されているのか私たちは疑問を持っているが、実態は胸を張れる事業になっているのか。この事業についての知事の考えをお聞きします。
継続性を担保するということでは、今回疑問に感じざるを得ないものも実際にはある。問題点をしっかり把握して、来年度以降市町村事業に移行するが、県が責任を持ってこの事業が拡充・引き継がれていくよう取組んでいただきたいと要望しておきます。
4【生活保護基準の切り下げの問題や影響について】
いままでも質問をしてきましたので今日は、生活保護基準切り下げ(見直し)の影響が様々な制度の利用者に影響があるという問題で1点だけ質問します。
子どもの貧困が広がり、貧困の連鎖も深刻であります。子どもたちがお金の心配なく学校生活ができるよう、就学援助制度や高校生に対する県の奨学金制度があります。この制度も生活保護基準が一つの基準になっています。そこで、基準の引き下げの影響を受けないよう、対象世帯の年収が生保基準の1.5倍以下であるという要件の緩和をして、対象が狭められないようにすべきと思いますが、この点を教育長にお伺いします。
たしかに奨学金の貸付制度については、生活保護基準の1.5倍以下という基準のみをもってしてこの制度に当てはめるのではないということは承知しています。しかし、生活保護基準の切り下げられたもとでこの1.5倍という数字があったことによって対象にならなかったということが無いように、ここは全国的にも基準の1.5倍という数字についてもの緩和をしておりますので、ぜひここを改めていただきたいと思います。
そしてその基準によって、多くの制度に影響が及ぶということに対して、下村文部科学大臣も、生活保護費の引下げに伴い経済的に困窮している家庭が、制度の適用を受けられなくなるおそれが出ているというふうに言っている。そして自治体で必要な対策を講じる様に促すという考えを示しています。そこで県から国に対して、そういうことであれば対策に必要な予算も合わせて要望をしていただきたいと申して一切の質問を終わります。
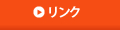

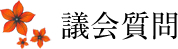 議会質問
議会質問