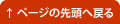9月議会一般質問
2013.10.02
9月議会一般質問
はじめに、県立4年制大学について伺います。
今県議会に、新県立大学基本構想の見直しを求める請願が9万数千筆の署名を添えてだされました。その請願には今回発表された基本構想は県内の3私立大学と競合するような学部・学科構成となっており・・・、私立大学の経営を圧迫し、県内高等教育全体の活力の低下につながるものと危惧するとまで記され、基本構想の見直しを求めています。しかし、私は、本県の進学状況と大学の設置数を見れば、少子化が進んでいるとはいえ、基本構想の内容が私学を圧迫し、競合するものになっているのかについては、請願の趣旨に疑問を抱いております。県としてどうとらえておられるのか、総務参事に伺います。
ご答弁のとおりですから、県民の皆さん、請願を出されたみなさんにご理解いただけると思いますので、引き続きご尽力をお願いします。
生活保護基準の引き下げの影響、審査請求について
生活保護費の削減は、生活扶助は、2013年度に初年度分151億円の削減を手始めに、2015年度まで3年かけて670億円、現行基準から6.5%の削減。さらに年末に支給される「期末一時扶助」は2013年度に一気に70億円分の引き下げをおこない、生活扶助と期末一時扶助を合わせると3年後には年間740億円、7.3%の引き下げを行うという、いまだかつてない大改悪です。
今回の生活保護費の削減は、すでにおこなわれてきた老齢加算廃止など対象が一部限られた削減ではなく、食費や水光熱費など日常生活費にあてる「本体」ともいうべき生活扶助基準の削減であり、これによってほとんどすべての受給世帯に影響が及びます。
そして、この生活保護基準の引き下げは「物価が下がっている」いわゆるデフレを口実にしておこなわれましたが、現実にはアベノミクスの経済対策によって電気代、ガス代など光熱費の値上げや、小麦・大豆など輸入原材料が値上がりしたことで食料品も高くなって生活を直撃している中で、8月支給分から生活保護費が削減された影響について、県はどのように把握しているのか。健康福祉部長に伺います。
反貧困ネットや生活と健康を守る会など、生活保護の受給者に寄り添った支援活動をしている団体から呼びかけられ、今月17日、全国一斉で審査請求がされました。その件数は、全国で約7000件、県内では52世帯62名です。
今215万人の生活保護受給者がおられますが、審査請求を呼びかけられた方々はわずかですし、実際に呼びかけに対しても、肩身が狭い思いをしているのにそんなことはできないとか、ある方は、自分自身が障がいを抱え小学生の子がいる家庭で今回1万3千円も減額になったが「生活をみてもらっているのにたてつくことはできない」といって審査請求されない方がおられます。そういう状況のなかで、やむにやまれず審査請求されたということを汲み取っていただきたいのです。
〈審査請求に県庁まで来られた方の生の声〉
私は、生活保護費が削られる前でも大恩人の葬式に顔をだせなくて、まして父親の葬式に顔を出せませんでした。その時の私の気持ちを是非、心に感じてください。そのうえ、子どもたちにも何もしてやれない。一食や二食、食べられないのは本当につらいけど、我慢できる。だけど心に負ったすまないという気持ちは死んで墓場まで持っていくしかない。
小さい子どもたちがいる家庭は親が自分は食べなんでも子どもに食べ物を食べさせてあげるが今年、来年、再来年と減額されれば、今度その子どもたちにも食べるものをあげられなくなるんです。
ご紹介したのはほんの一部の声です。
○審査請求の申し立てをした方々の切実な声を県はどのように受け止めたのか。健康福祉部長に伺います。
生活保護は、最後のセーフティネットであり、生活保護受給者が215万人と過去最多にのぼったことは年金や雇用保険など社会保障制度が脆弱であることと、雇用情勢の悪化の顕れです。根本の問題の解決なしに、政府は生活保護費の大幅削減を実施しました。
今年の削減にはじまり、来年、再来年とさらに生活保護費を削減する方針です。このまま実施することは生保世帯の生命にかかわる状況をつくりだすことが危惧されます。県として生活実態の現状をとらえ、今回の削減と、来年、再来年の更なる削減を見直すことを国に求めるべきと思います。健康福祉部長いかがですか。
審査に当たっては、請求者の声と実態をつかんでいただき、法律の精神に基づいて適正に審査をしていただきくよう要望します。
地域定着支援センターについて
法務省の「矯正統計年報(2011)」によると、約7万人が受刑中で、このうち新規受刑者が2万6千人、その約58%が再犯といいます。また、帰る場所のない満期釈放者の中には高齢者や障がい者が1,000人ほど含まれています。帰住先のない人の約57%が、1年未満で再犯をしているというデータもあります。
刑務所などの矯正施設には、福祉サービスが必要な高齢者や障がい者が数多く入所しており、その人たちが犯罪に至った背景に、低学歴、学力不足、家庭崩壊、職業能力不備、コミュニケーション能力の欠如、不安定雇用など身体的、経済的、社会的な問題が複雑に絡み合って、自立生活を阻害する多くの課題が隠されています。
そうした課題を抱えた人は、これまで矯正施設を退所しても、誰も迎えに来てくれない、お金もない、行くところもない、仕事もない。自力では必要な福祉サービスにもたどり着けない高齢者・障がい者が多く、再犯→矯正施設を繰り返し、窃盗など軽微な犯罪を繰り返し、通算して何十年も刑務所でくらして80歳を超える人もいる状況です。
このような矯正施設を退所後、行くあてのない高齢者・障がい者の方に対して、入所中から本人の意向を聞き、地域で生活できる支援体制を関係機関と事前に調整し、支える機関が必要ということで国は各都道府県に「地域生活定着支援センター」を設置しました。
昨年度から業務を委託された長野県社会福祉士会は、福祉士会の事務所内に地域生活定着支援センターを置いて、手さぐりで業務を始められました。所長さんから、私たち県議団にもセンターの活動を知ってほしいと話がありました。
センターの事業費は10分の10、国からの補助金で運営しており、昨年は1700万円で約3人で業務をしているが、コーディネイト業務・フォローアップ業務・相談支援業務や満期出所者の迎えなど多忙を極めて、3人ではとても回らないとお聞きし、昨年9月県議会前の知事への申入れで予算と体制の拡充を要望したところ、今年度は、2500万円に補助金を増額し、6.5人態勢でセンターの機能の充実をしていただきました。この取り組みを県はどうとらえているのか。健康福祉部長にお伺いします。
予算の増額によって人員を増やし、すでに今年度は8月末で昨年度実績かそれ以上の実績を上げているところです。
ところが、地域生活定着支援センターの委託料に充てている国の補助金について、国は、9月11日付で「平成25年度セーフティネット支援対策事業費補助金の内示について」という厚労省社会・援護局保護課長名で通知がだされました。
その通知では、生活困窮者支援モデル事業、生活保護基準改定に伴うシステム改修等に局内の予算を優先配分した結果、優先配分以外の事業については、総額で約3割の不足が生じることとなった。
「セーフティネット支援対策事業費補助金」は予算の範囲内で国庫補助を行い事業であり、現在のところ、これを超える内示の見込みはないため、優先事業以外は約9か月分の内示を行うこととする。と言う・・にわかには信じられない内容です。
地域生活定着支援センターの事業は補助金は10分の10で、今年度2500万円の3割、750万円減額です。
これについては、県が予算措置すべきものではないと考えます。県は、この年度途中で減額により不足するセンター事業費をどう財源手当てするのか。お伺います。
また、セーフティネット支援対策事業費補助金を活用しているほかの事業費もセンターと同様に3割減額になるわけですが、どのように補うのかもお聞きします。
あくまでも国に今年度分補助金予算の満額の執行を要求すべきと考えます。健康福祉部長に伺います。
厚生労働省は、通知の最後に「なお、既存事業の実施について、職員の人件費等事業の実施に最低限必要な経費については確保するなど、事業実施に支障がないようお願いしたい。」と無責任な態度です。本来、国が財源手当てすべきものとだけいっているわけにはいきません。県としても検討はしていただきたいと申し上げておきます。
県は、全国に先駆けて精神障がい者の地域移行に取り組んできました。10年前から4病院でモデル事業を実施し、平成18年から精神障がい者退院支援事業に、翌19年から県単独事業で退院支援コーディネーターを置き退院支援事業を行ってきました。国は県より1年遅れて事業を開始したように先進的な役割をはたしてきました。
とはいえ、精神科病院の入院期間は、1年以上5年未満が約60%、そのうち2年未満が30%ですが、最長は45年9カ月で、平均入院期間は7年7ヶ月。長期間にわたって入院しているため、退院することは容易なことではありません。
ご本人や家族、病院、行政や地域の支援者や支援団体などを、きめ細やかにつないでいく地域移行コーディネーターの役割は大きなものです。
退院を躊躇している人も、支援をしっかり行えば地域で暮らせる方が多く、「退院してよかった。退院後もヘルパーやグループホームの世話人がケア会議をしながら支援してくれて安心」「43年間入院していましたが、退院支援で退院しました。」というように、地域の生活に喜びを感じておられます。
まだ、多くの方が精神科病院の中で退院をあきらめて暮らしています。県には病院との連携を強め、地域移行支援の充実を図ってほしいわけですが、支援に当たるコーディネーターが大事な役割を果たしていることについて、どうとらえているのか伺います。
県が全国に先駆けて精神障がい者地域移行を行ってきたわけですが、昨年度まで補助事業で県下5か所に配置されていたコーディネーターが、障がい者自立支援法への移行の経過のなかで今年度のコーディネーター配置は4エリアとなりました。今後は市町村事業として位置付けられるということですが、市町村で体制が整うのでしょうか。小規模な自治体では体制を整えるのは厳しいと思いますが県としてどう支援していくのか、また、市町村の体制が整い、市町村でコーディネーターが育つまで県として支援をしてほしいと思います。健康福祉部長に伺います。
補助金によって精神障がい者地域移行・地域定着支援事業が行われてきましたが、障がい者自立支援法・障がい者総合支援法へと移行して、個別給付に代り、実施主体が市町村へと移行していくなかで必要な支援が継続していくことを県として保障してほしいと思います。
また、来年度の精神保健福祉法改正に伴っても地域移行コーディネーターの充実した配置を望む声があります。引き続き、県の役割は大きいのでよろしくお願いします。
18日にJR東海がリニア中央新幹線の路線や駅位置も示された環境影響評価準備書を公開し、20日から準備書の閲覧が始まりました。また、10月2日からは、リニア沿線の12カ所でJR東海による準備書の説明会があり、11月5日までは県民がJR東海に意見を寄せる期間ということです。
今日までの県議会でリニアに関連しては、2027年リニア中央新幹線開業に間に合わせるには「残された時間は多くない」といわれた牧野飯田市長の認識にみられるように、リニア駅の整備と周辺整備やアクセス道路の整備、さらにJR飯田線とリニア中央新幹線が交差する付近への駅整備、それらも含めた都市整備をどう進めていくのか、だれが主導していくのか、調整するのか、かかる予算を国・県・地元自治体はどう負担するのか。リニアで東京・名古屋が時間的に近くなることで変わると思われる観光や経済活動をどうするのかという質問が目白押しでした。
しかし、県は準備書に対する知事意見を作成するため10月下旬には動植物や地質などの専門家によって県環境影響評価委員会を開くことをはじめ、準備書の内容について審議を行うわけです。南アルプスを貫く長大トンネル建設など巨大開発や中央構造線を横切る工事など、環境に及ぼす影響は厳しい審議を尽くすことが必要だと思います。
また、JR東海から出された準備書に県民の意見・地域住民の総意を反映させることが大事なことではないでしょうか。
路線や駅の地点が示された今、県として、県民に情報を周知すること。県民の意見をJR東海に伝えることにも力を入れて欲しいと思います。知事にお伺いします。
2027年開業。このゴールに向かって、環境への影響の不安、周辺整備への不安。財政負担等の不確定要素を多く残したまま、建設へ見切り発車。一部には2020年東京五輪までに一部区間だけでもなどという強引に建設を前倒しすることがないよう、国やJR東海に働きかけるべきと考えます。知事にご所見を伺います。
今回は生活保護受給者や矯正施設からの退所者の地域生活定着支援、精神科病院に長期入院されている方の地域移行ということを中心に質問をさせていただきました。いずれも自分から声を出して困っていることを訴えられない、どうしたら自分に必要な支援を受けられるかわからない、というよりそういう支援があることも知らないというなかで、より困難な状態になっていく、人に対して、国は社会保障予算が増大し続けているからと予算を削減する。受けられる支援をはずしていく。
それなのに、「税と社会保障の一体改革」の名で収入のない人にも「公平」に消費税増税をする。
弱者を切り捨てるようなやり方に強い憤りを感じます。
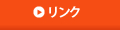

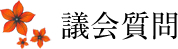 議会質問
議会質問