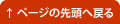2013年2月議会代表質問
2013.02.28
安倍政権に対する知事の政治姿勢について
日本共産党県議団を代表し、代表質問をおこないます。
安倍政権発足後に行われた県民世論調査で、安倍政権に一番やってほしいことは、震災復興75%、第二は景気・経済対策68%です。
まず震災復興についてお伺いします。
東日本大震災から間もなく2年を迎えます。いまだに32万人もの方々が避難生活を余儀なくされています。私は1月30・31日、福島県いわき市で緊急に開催された「小さくても輝く自治体フォーラム」に参加した際、東電福島第一原発の立地自治体の隣町、富岡町へ防護服を着て視察することができました。震度6強の地震と21mの巨大津波での大災害の後の原発事故から2年、1万6千人の町民は福島県内はじめ46都道府県に避難生活を余儀なくされ、一時帰宅には防護服で放射線測定器が離せません。町は5年間戻れない宣言をしています。東電の賠償、除染、震災によって壊れたインフラの復旧などなど、復興の道のりも見えない状態です。浪江町長や富岡町長から、2年経って忘れられるのが怖い「福島を忘れないで欲しい」原発は「福島が原点で考えて欲しい」との言葉を胸に深く刻んできました。「原発ゼロ」への政策転換を強く願うものです。
震災復興への長い道のりです。原発事故によって、放射能による子ども達の健康被害の不安がいまもあります。屋外で思い切り体を使って遊ぶことや運動をすることもできません。内部被ばくも大変心配です。福島の子供たちは、日々、見えない放射線にさらされて遊ぶ場もままなりません。数日間でも放射線の心配がない地域で過ごせば、被曝線量は下がります。春休み、夏休みなど長期の休みに子ども達を受け入れる取り組みを民間や市町村と連携して、長野県として継続的に行うってほしいと思います。知事はいかがかお考えですか。
いまだ先の見通しが全く持てず避難が長期化しているにもかかわらず、今年度末で高速道路無料など支援の打ち切りがあります。もう忘れられてしまうのではないかと不安を抱いておられます。県内への避難者の方々に寄り添っての支援など、県として今後どのように支援していくのか。また、国には支援策を縮小しないように要望してほしいと思います。いかがですか。
また、東日本大震災翌日未明に震度6強の大地震に見舞われた栄村は、昨年末までに震災復興住宅が完成し、仮設住宅や村外に避難されていた30世帯が入居しました。その他、農地復旧への手厚い補助など様々な支援は東日本大震災の復興に先駆ける取組になっています。知事は提案説明で、栄村復興基金や国の復興交付金を効果的に活用しながら、住宅の自力再建や生活支援を行うと言われ、心強いことです。震災復興のカギは住宅再建であり、栄村での取組を生かすように、被災者生活再建支援制度の拡充を国に求めるとともに、県でも独自の支援制度の実現を図ることが必要と思います。震災復興への知事の所見をお伺いします。
経済対策について
安倍総理の経済対策「アベノミクス」は「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」を「3本の矢」といい、「円高・デフレ不況から脱却し、雇用や所得の拡大を目指す」と繰り返し言われています。
安倍政権発足から2か月、株高、円安に動いていますが、株高・円安が進行している状況を景気回復ととらえていいのでしょうか。現在進行している株高は投資部門によるものです。先月25日までの2か月間の株式売買で約58兆円の売りに占める海外投資家の割合は約34.6兆円と6割で、週末に利益を確保する売買が中心です。さらに、急激な円安で輸出関連企業は利益を確保したと言われていますが、逆に多くを輸入に依存しているエネルギー・食糧・資材などの高騰を招き、国民生活や企業活動を直撃しています。
アベノミクスでデフレを克服するとしていますが、10年以上にわたってゼロ金利政策を続け、日銀が大量の国債を買い入れる量的金融緩和を行ってもデフレ不況を克服できずに今日に至っています。公共事業については経済波及効果は1.63倍程度にとどまっています。国庫補助事業は県も県債の発行が伴い厳しい県財政に拍車をかけることにつながります。成長戦略の具体化はこれからのようでありますが、大企業への減税や、海外進出企業への支援などで実効ある経済政策といえるのか疑問です。景気・経済対策において、アベノミクスが景気浮揚に結びつくのか疑問であります。
「デフレ不況から脱却し、雇用や所得の拡大を目指す」には、デフレの原因をつかんで対策することが必要です。
昨年の勤労者の平均賃金は、1990年以降で最低になり、ピーク時の1997年より年収で70万円も減っています。総務省が発表した2012年の労働力調査で非正規雇用労働者は35.2%と過去最高になり、年収200万円にも満たない労働者が1000万人を超えています。10年余りの間に、平均でも月給2か月分程度収入がなくなったことになり、ローンや教育費などが家計に重いものになっており、労働者の暮らしの悪化は深刻です。賃下げ、非正規雇用の拡大がデフレ不況の悪循環をつくりだしている最大の要因と考えます。デフレ脱却のためには、賃上げと安定した雇用の拡大が重要と考えます。知事の所見をお伺いします。
消費税について
安倍内閣は、日銀と共同して、インフレ目標を2%に定めて、金融緩和と財政出動によって2%目標を達成しようとしています。しかし、デフレ不況にたいする「処方箋」をあやまれば一層、格差と貧困を拡大してしまいます。
現状では、内需を下支えする国民所得が上向く要素はありません。円高によってじりじりと物価は上がり始めていますが、賃金も年金も下がるばかりです。さらに社会保障の給付の削減、負担の増加で可処分所得は減るばかりです。こういう状況のまま、2014年4月から消費税8%に引き上げられれば景気の底が抜けてしまうのではないかと危惧しています。消費税増税は中止すべきと思います。知事のご所見を伺います。
公務員給与問題
国家公務員と同様に地方公務員の給与引き下げを国が地方に求めることは地方自治法違法ではないかと思います。しかも、国家公務員の給与削減は東日本大震災の財源の一部にあてるためとして2年間限定で引き下げられるというもので、これに連動させて地方公務員の給与削減を国が求めるのは二重三重に通らない話であります。
長野県では、すでに行財政改革によって職員を減らし、給与・手当等を引き下げてきました。
国が地方公務員の給与削減の手段として交付税を減額するようなやりかたは交付税の補助金化だと指摘されるように交付税の趣旨からも逸脱しています。
また、長野県では直接影響はありませんが、退職手当債の発行可能額を圧縮して国主導で地方公務員の退職にまで国が踏み込むのは地方分権に逆行するものであり、地方の裁量権が著しく奪われるものとして看過できません。地方公務員の給与引き下げは、デフレ不況に拍車をかけるものです。国が交付税減額によって強引に押し付けることは、地方自治の根幹を壊すものではないでしょうか、知事のご所見をお伺いします。
憲法に対する知事の姿勢
安倍首相が国会質問で憲法問題について問われ、憲法96条をまず改定すると答弁しています。憲法96条は憲法改正の手続きを定めた条項で、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」としています。この3分の2以上から2分の1にハードルを下げる、発議要件の緩和をすることで、改憲を進めようという狙いは明らかです。
安倍政権は6年前の第1次政権のさい、国民投票の手続きを定めた改憲手続き法の制定を強行しました。発議要件の緩和は、それに続くものです。第1次安倍政権で改憲手続き法の制定から、憲法9条を含む改憲に突き進もうとしたことに対し、国民的に改憲を望まない世論のなかで、憲法9条を守ろうと9名の著名人が呼びかけて「九条の会」が全国津々浦々に広がり、第一次安倍政権は改憲を断念しなければならなかったという経験をしています。
日本国憲法は、第二次世界大戦でアジアの人々2千万人、日本国民310万人が尊い命を亡くしました。こんな悲劇を繰り返さないため、憲法9条を含めて制定されました。
特に、長野県は満蒙開拓団や青少年義勇軍に3万人を超える人々を送り出し、その数は全国一です。およそ半数の人々は祖国に帰れませんでした。
そういう歴史がある、長野県民は平和への思いは強く、長野県内では200を超える憲法9条を守る会がつくられ、県民過半数署名にとりくみ、講演会や憲法学習会など様々な活動が行われています。県民世論調査の結果で安部政権にやってほしくない政策の一番は改憲です。知事の所見をお伺います。
新年度予算案について
2013年度当初予算案は、総合5か年計画(中期総合計画)の初年度に当たります。予算規模8,299億円、対前年度113億円減(-1.3%)で、3年連続の緊縮財政の様相です。しかし、実際は同時に発表された2012年度2月補正予算案(経済対策分)450億円と一体で見ると、予算規模は8,749億円となり、対前年度337億円増(+4.0%)と積極予算になります。
歳入面では、地方公務員給与の削減を前提とした影響額58億円を含め地方交付税が102億円の削減です。地方交付税の大幅な減額などに対応するために基金の取り崩しがされます。当初予算で見る限り、県債全体が縮小しているのに、臨時財政対策債は今年度を23億円上回り、713億円にも上り、県債の57%を占めるという異常事態になっています。知事も臨時財政対策債は国に廃止を求めているわけですが、使わなければ予算編成ができない状況で県債残高は、普通会計でみても、25年度には1兆6115億円になり、目的別歳出に占める公債費は17%と民生費13%、土木費11.9%より大きな割合になっています。このような財政状況について知事のご所見を伺います。
交付税の大幅な減額、県税収入は若干の伸びを見込んでいますが、県財政は今まで以上に硬直化し、地方自治体の独自の施策ができないということにならないかと危惧しています。阿部知事の下で、今後5か年の総合計画と予算をリンクさせる施策の実施や、新年度中学3年まで実施される30人規模学級など県独自の政策、さらに長年、県民からの要望がある「子ども医療費の窓口無料化」なども実現させていただきたいわけですが、平成25年度予算と2月補正予算を併せると、県債発行額はさらに増え、国からの交付税は減らされ、臨時財政対策債を使わなければならず、ゆがんだ財源の構造になっています。
このような自由度のない硬直した予算では、県民の要望に基づいた県独自の施策を展開することができません。自治体の独自裁量を生かすためにどのような工夫をされているのか知事にお伺いします。安倍政権の進める経済対策として、公共事業の増加が見込まれますが、国の補助事業には県債の発行が伴います。慎重にならざるを得ないと思います。知事の所見をお伺いします。
(中期総合計画)総合5か年計画について伺います。
今後20年間に県内で30万人もの急激な人口減少が見込まれている。
5か年計画の現状認識、時代の潮流で、到来した人口減少社会とされており、「人口減少」は避けて通ることができない「宿命」のように記載されています。
我が国の総人口の伸び率は、未婚化・晩婚化の進展などに伴い昭和49年以降の長期的な出生率の低下により、徐々に鈍化してきた。と状況分析があります。それは、結婚・出産に対する価値観の変化によるものであり、個人的な理由に基づく、結婚に対する意識の変化と、個人の価値観に置き換えてしまおうというものです。しかし、いま若い世代の2人に1人は非正規雇用で、不安定な雇用とワーキングプアが1000万人といわれるように低所得に置かれています。親の元に居れば何とか暮らせるという状態から抜け出せない状況に置かれています。とても結婚して家庭を持つことができない状態ということが大きな要因として挙げられます。結婚・育児をとりまく環境の悪化など人口減少に至る現状認識を持っておられるのでしょうか。要因の分析がされてこそ、有効な対策を講じることができるのではないでしょうか。知事に伺います。
5か年計画の男女共同参画社会の実現の達成目標として数値目標が明記されました。
県職員の係長以上に占める女性の割合を、現在9.4%から28年度12%(5か年計画ですが、H29年度の目標値は次期長野県男女共同参画計画の策定に合わせて検討するということで4年間の目標がしめされています。)
また、公立学校の女性校長・教頭の割合は、H29年度目標で、小中学校で12.7%から15%。高等学校で6.2%から7.0%と数値目標が明記されました。
ちなみに、民間企業の課長相当職以上に占める女性の割合はH22年度9.1%からH29年度は13.0%と目標が記されています。
県が次期の男女共同参画計画の策定との関係でH28年度までの目標12%になっていますが、12%を着実に28年度までに達成し、民間企業がH29年度までの目標値13%をめざしているのですから、県職員の目標は29年度には民間企業以上の目標の実現をしていただきたいと思います。いかがですか。
3年前の私の代表質問に対して、当時の県警察の女性警察官の警部・警部補などへの昇任についていただいたご答弁では、県警察は男女の如何を問わず、競争試験によって昇任が行われていること。県警察の女性警察官の採用は、平成元年から開始し、平成21年度女性警察官は180名、その比率は警察官の5.3%、またその平均年齢は約30歳であり、男性警察官の約40歳と比較して、若いが、女性警察官180名のうち、巡査部長に36名、警部補に4名を登用しております。また平成21年3月には、警察署の課長として、実働部門の指揮官となる警部が女性警察官から初めて登用されております。とご答弁をいただき、その後も着実に進んでいると思われます。それは、実効性を担保する人事制度になっているからだと考えます。
5か年計画には、男女共同参画で達成目標を盛り込んで、県自ら率先して目標を達成していくために、実効性を担保することが肝要です。その方策はあるのか。総務部長・教育長にそれぞれおうかがいします。
子育て先進県と言われますが、経済的な子育て支援も必要と知事は認識されておられると思います。県民の要望も多く、県内の自治体では県の対象年齢に上乗せして独自の努力をして対象年齢の引き上げをして頑張っておられます。子ども医療費の窓口無料化を繰り返し求めてきたが、いまだ実現に至らず大変残念であります。厳しい財政ではありますが、中期総合計画の策定や新年度予算編成の際は何らかの検討されたのかどうか、健康福祉部長にお伺いします。
自然エネルギー産業に進出する企業の支援について
自然エネルギー分野は、ものづくりの観点からも市場として、特に内需拡大が期待でき、有望な分野のひとつと位置付けて、長野県ものづくり産業戦略プランにおいても、今後の産業振興の重点分野の一つとして環境分野を位置づけています。
工業技術総合センターで企業から様々な相談を受け、具体的な技術的助言をされていますし、長野県テクノ財団においても、ものづくり産業の優れた超精密加工技術などを活用して進出すべき分野を選んで、地域産業への指導や研究活動を展開されているところです。自然エネルギー産業の振興に積極的に取り組んでいただいています。
長野県の製造業は、
全国的に製造業の集積地といわれている東京都大田区や大阪府東大阪市と比較しても、諏訪地域や上伊那地域は、従業者数や製造品出荷額は上回り、引けを取らない実力があり、「ものづくり信州」が裏打ちされています。製造業の集積した力と、部品製造の実力はいくつもの指標で全国トップレベルを占めています。
自然エネルギーに関連した産業を県としても産業振興の重点分野と位置付けているわけです。さらに、5か年計画には自然エネルギーによる発電設備の容量でみるエネルギー自給率を平成22年の58.6%から、70パーセントという目標が明記されています。この目標を達成するために、県内に多く存在する技術力の高い製造業の技術を集積して、大企業の下請けではなく成長分野である自然エネルギー分野での産業と雇用の創出、県内製造業が主体的に関わっていけるように県が積極的にコーディネートを行うべきと考えるが、商工労働部長にお伺いします。
社会資本の整備について
すでに、全国各地で問題が表面化している公共構造物の老朽化への対策について伺います。
社会資本の老朽化対策の必要性は以前から言われていましたが、道路・橋梁など建設には補助金がついても、維持管理費は地方自治体が負担するということで、維持管理・改修は遅れているなかで、昨年12月に起きた中央自動車道・笹子トンネルの天井版崩落事故をきっかけに社会インフラの老朽化の対策が差し迫った課題になりました。
高度経済成長期に大量に造られた道路・トンネル・橋梁はじめ県有施設などがいっせいに寿命を迎え、安全に使い続けるためには維持管理や改修にかかる莫大な費用をどう確保するのか、国・地方自治体に迫られています。安倍政権は、経済対策に老朽化対策を含めて公共事業に重点的に投資をするとしていますが、県は社会インフラの老朽化の全体像を把握し、維持管理や改修の長期計画をもって進めていかなければなりません。社会資本の長寿命化対策をすでに検討されてきましたが、全体の状況を把握しているのか、お伺いします。
東京の府中市は、インフラの老朽化状況を詳しく調べたうえで、比較的短いスパンで定期的に修繕など計画的な維持管理を行って少ない予算で寿命を伸ばすという、「インフラマネジメント計画案」をまとめたと聞きました。
社会資本の老朽化対策について、国の経済対策に社会資本の重点的な整備と適切な修繕が盛り込まれていますが、長期計画をもって進めていくために、老朽化している社会資本の情報を整理・把握し、改修と計画的な維持管理を図るための制度の構築と、県が管理する社会資本の改修工程表を整備して、確実に改修を進める必要があります。あわせて、そのための財源の保障が必要です。維持管理が地方任せになっている国の体制、補助制度の見直しを国に求めるべきと考えますが、建設部長に伺います。
使いやすい住宅リフォーム助成制度と県産材の活用について
共産党県議団は、繰り返し知事に対し経済対策としての住宅リフォーム助成制度の実現を求めてきました。しかし、知事は「単なる経済対策だけでなく、明確な政策目的を持って実施することが必要」とのべ、県産材の利用拡大を柱として制度を構築し、今年度実施されました。住宅リフォーム助成制度の予算額5000万円の執行状況はいかがか。建設部長にお伺いします。
県が実施している信州型住宅リフォーム助成金は、条件が厳しく利用が進んでいない。この際、経済活性化の効果もある住宅リフォーム助成金と、県産材の利用促進とを切り離し、利用の条件をシンプルなものとした上で、運用する方が、効果的ではないかと考えるが、いかがか。建設部長にお伺いします。
一方で、住宅への県産材利用促進も重要な課題であるので、新たに県産材を活用した住宅等への支援策を打ち出す必要があると考えるが、林務部長にお伺いします。
住宅リフォーム助成制度の質問の際、幾度かご紹介してきた秋田県の施策でありますが、すでに秋田県は今年度まで3年間実施してきました。秋田県の制度は、工事内容を特定せず、工事費の10%、限度額20万円、ただし一世帯につき20万円以内であれば制度を何度も利用できるというものです。(秋田県の25市町村で22市町村が定めた制度との併用ができます。)この結果、制度開始から34カ月で、3万9,539件の申請があり、合計補助額53億6778万円。工事額は790億1522万円。補助効果は14.7倍。経済波及効果は23倍、1240億円にもなっています。
この制度を通じて、秋田県知事は○県民の住環境が改善された。○中小工務店の受注で県内経済の活性化に寄与した。○全国から注目され(視察も多い)全国各地に制度が広がった。と「一定の成果を上げた」と言われ、4年目になる2013年度も13億9000万円の予算を計上し事業の継続を提案されました。
知事は、住宅リフォーム助成制度と県産材の利用促進を今一度整理して、それぞれ効果の高い制度として進めていこうという考えはないのか、改めて知事にお伺いいたします。
長野県保健医療計画について
従来は7つの個別の計画であったものを、今回一体化して「信州保健医療総合計画」として取りまとめ、示されました。「長生き」から「健康で長生き」へと目指すべき姿も示されました。
長野県は、全国トップクラスの長寿県であります。それは、地域に根ざして、生活改善活動や予防医学まで取り組んできた地域医療や保健補導員や食生活改善推進員の方々の活動によるところが大きいものがあります。今後もその力によるところを県として再確認して、支援を強めていただきたいと思います。
また、計画案では、がん、脳卒中、心疾患といずれも療養は、在宅療養を打ち出しています。さらに、患者の生活を支えるため、医療保険サービスと介護保険サービスを連携させ一体的にサービスを提供する、地域包括ケア体制の整備も打ち出されました。これらのサービスは患者の立場にたって充実させることが肝要であります。しかし、現実には、社会保障費の抑制のため、医療機関の基準病床の削減ありき、医療費の削減ありきではないのかと懸念するものであります。
地域包括ケア体制を整えるとのことですが、今以上にマンパワーの拡充が必要になります。県下各地の医療機関では医師・看護師の絶対数は不足しており、医師・看護師の確保に大変ご苦労されています。介護の現場も介護職員の慢性的な不足に悩まされています。
地域的な偏在の問題も含め、人材の育成と確保を、県として今後どのようにされるのか健康福祉部長にお伺いします。
県民の生活困窮について
生活困窮者支援と生活保護について伺います。
はじめに昨年度、今年度と実施していただいた生活困窮者の「絆」再生事業は来年度も継続していただくことになりました。先日、私たち共産党県議団が主催するかたちで「ストップ!格差・貧困 生活支援ネットワーク交流集会」をおこないました。
反貧困の生活支援ネットワークの活動は、リーマンショックで多くの派遣労働者が職を失い、住まいもないという事態をうけて、2009年の年末に東京日比谷公園でおこなわれた年末派遣村に始まって、県下各地で生活困窮者支援の相談会や年末絆村などにとりくまれてきた活動の交流会でしたが、県の絆再生事業も活用してがんばっていることやパーソナルサポート事業も大変大事な事業であることを再確認しました。県が事業の継続をすることは地道な活動をしているみなさんに大きな支えであると思います。さらに、新年度は自立のための寄り添いサポート事業で、寄り添いサポーターがアウトリーチで支援することになり大変うれしく思います。
しかし、国は生活保護予算を削減する方針を決めたことは、憲法に謳われている「最低限度の生活」が際限なく切り下げられるのではないかと懸念しています。
厚生労働省は、生活保護の生活扶助を2013年度から2015年度まで3年間かけ、現行基準から6.5%(7.3%)引き下げるというのは、生活保護制度が始まって過去2回の引き下げ2003年0.9%、2004年0.2%と比較にならない大幅なものです。
低所得者世帯の消費水準と比較して生活保護基準が高いからと、生活保護基準を引き下げるという審議会の基準の見直しは90億円削減で、これ自体も認められないものでありますが、今回の削減額670億円のうち580億円は08年から11年までのデフレ分を反映させるということで削減額が6倍以上にもなっています。
低所得者にとって本当にデフレなのかということです。パソコンや家電製品の下落はあっても、生活保護世帯では買えないものばかりです。むしろ食費や水光熱費、灯油など基本的な生活費はデフレどころか円安の影響で値上げが心配されるところです。
生活保護基準は、最低賃金、課税最低限、就学援助制度はじめ様々な基準を定める際にも用いられており、国民の最低生活を守る岩盤として、社会保障制度の要です。生活保護基準を引き下げれば、国民の最低生活を守る岩盤の意味を失い、際限なく国民の生活水準を引き下げるデフレスパイラルに陥る状況をつくりだすものです。
社会保障と税の一体改革の「社会保障改革推進法」では、自助、共助が前面に打ち出され、国による生存権の保障である憲法25条を解釈改憲するものであるともいわれていますが、厚生労働省が示した生活保護基準の引き下げの方針はまさにそのものではないでしょうか。
国に対して、県から生活保護削減の方針を見直すよう要請してほしいと考えます。健康福祉部長に伺います。
警察の不祥事防止対策について
長野県警察においても、今年度、残念ながら警察官の不祥事が相つぐ事態となりました。県警は、県警本部長を責任者とする対策本部を設置し、新たに50数項目に及ぶ対策を検討し、再発防止に取り組んでいます。本来、県民に規範を示すべき職務に携わる警察官の不祥事は、大変残念なことですが、問題は、再発防止のための自浄能力がどれだけ発揮されるかにかかっていると思います。その意味で、新たに検討された対策の効果に期待するものですが、当事者である警察官自身の受けとめをはじめ、検討後の対策は、どのように警察業務に生かされているのか。県警本部長にお伺いします。
犯罪のない、安心して暮らせる長野県であることは県民すべての願いであり、そのために県警察が果たすべき役割と責任は大きいと思いますが、今年度の犯罪認知件数や検挙率などをはじめとする警察業務に、不祥事根絶のための新たな対策によるとりくみは良い効果をもたらしていると言えるのでしょうか。昨年中は、犯罪検挙率・解決率の向上、交通死亡事故の減少など成果は上がっているとのことです。不祥事による警察への不信を払しょくし、防止の検討をうけて、職員の意識改革がなされた結果、職員のモチベーションを上げるような対策であったかお伺いします。
不祥事の再発防止のための自浄能力を発揮していくためには、研修などのいっそうの充実が必要と思われますが、いかがでしょうか。長野県警では、警察学校の研修で、実際の犯罪被害者の遺族の体験談を聞く取り組みがされており、警察業務のあり方を考えていくうえでも貴重なとりくみだと思われます。今後も継続されるのか。お伺いします。
教育の問題について
教育は、子どもの発達と人権が保障されること。学校は子どもたちにとって安心・安全な場所であること。をだれもが願っています。
教員の不祥事に心を痛めているのは、大人だけでしょか。子ども達も心を痛めているのではないでしょうか。
昨年7月、知事部局と教育委員会が共同で設置した「教員の資質向上・教育制度あり方検討会議」で、外部の視点から教員の倫理向上策や教育制度のあり方等について議論をしてきたところですが、検討会の専門部会での議論も保障されているのでしょうか。議論が途中なのに結論をまとめようとしているのでないかという委員の声も聞かれます。
知事は来月、年度内には検討会議から提言を受けて、具体的な行動計画を早急に策定する。有識者による委員会で行動計画の進捗状況を確認して、教育の再生に向けた取り組みを着実に実行していく。としていますが、検討会議の議論を十分保障することが大事ではないかと思います。
また、行動計画は庁内のみで策定するのでしょうか。学校現場や保護者を含め、県民的な議論をする機会を設けるべきではないでしょうか。教育長にお伺いします。
教育委員会は、この年度内に、あり方検討会議からの提言を受けて、具体的な行動計画を早急に策定するとしているが、あり方検討会議の議論の経過も知事は教育委員会から聞いているのですか。検討会に拙速な結論を求めず、もっと十分な議論を尽くすことが必要と考えるものですが、知事はいかがかお伺いします。
教育に体罰は絶対にあってはならない。
部活動で体罰がある。このことが、大阪市の桜ノ宮高校の事件でクローズアップされました。その桜ノ宮高校で文部科学省の義家弘介政務官が視察した際に、「強くなるための部活の体罰は一定ある」「ありうる体罰とそうじゃない体罰の線引きが必要」などの発言をされたそうです。体罰を容認する根深い体質に驚きます。
学校教育法では懲戒としての体罰を明確に禁止しています。
政府が1948年に示した体罰のガイドラインでは、殴る、けるはもちろん、長時間の正座や立たせることなど、生徒に身体的苦痛を与えることを体罰として禁止しました。しかし、81年、東京高裁は口頭の説教で生徒に訴える力に乏しいときは、教師は「有形の力」を行使してもよい主旨の判決を出し、体罰を容認してしまいました。
2007年に、文部科学省は教育再生会議の意を受けて、学校教育法の体罰禁止を骨抜きにする通知を全国の教育委員会に出しました。ここでも、体罰禁止といいつつ「有形の力」の行使を認めるという矛盾したものでありました。それらの経緯があったとしても、教育長は、体罰は許されないという認識でおられることと思います。様々な形で繰り返し...一定の体罰は仕方がない。という考え方を一掃しなければならないと思います。当初の理念に立ち返って、改めて体罰の定義を明らかにして、教育の現場はもとより社会的にも意識改革をする必要があると考えるが、教育長のご所見と決意をお伺いします。
体罰の問題が報道されるなか、元巨人軍の桑田真澄投手がどんな体罰も絶対にあってはならない。体罰でスポーツ選手が強くなることなどない。とキッパリ発言され、私は感動しました。桑田・清原選手の甲子園の活躍を同年代でテレビ観戦していましたが、高校一年のときから野球の名門校でエースピッチャー、巨人軍の投手として活躍された時以上に素晴らしいと思いました。
スポーツを通して心身共に成長し、競技の技術も向上させるために、学校の部活の見直しと、指導者の養成が必要と考えます。教育委員会では
子供の成長・発達にあわせた部活動の改善を図ることについて、現在検討を進めていると思いますが、どのような検討をされ、今後どう具体化していくのか、教育長にお伺いします。
最後に要望します。
長野県内にもいくつものプロスポーツチームができ、活躍していることは、スポーツ振興や地域活性化にメリットがあり、将来の自分を重ねて夢を抱いている子ども達も多いと思います。
しかし、体育施設が不足しているために、プロクラブチームに練習グランド、体育館が占有され、既存の地域クラブの活動を充足できないという声もあります。
地域クラブで長年にわたって地道な活動をしている指導者は、スポーツを通して、心も体も一流の人を育てたい、その思いで小中学生を中心に地域クラブの指導に熱心に取り組まれておられます。地域クラブから卒業していった子たちが、成長してやがてまた地域に戻って一緒にクラブの指導者になるという循環の中にやりがい、喜びを感じておられます。勝利至上主義ではなく、いろんな個性があるから、いろんな個性を大事にしながらの指導をされます。しかし、施設の不足や高すぎる利用料などに苦慮されていることも心にとめて、スポーツ文化をはぐくみために県として支援する方法を考えていただきたいと要望して、質問を終わります。
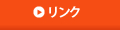

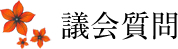 議会質問
議会質問