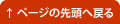2012年2月定例会 1
2012.02.29
1.介護保険について
2000年に施行され12年目になる介護保険ですが、昨年は2005年以来2度目となる介護保険法の改定がされました。また3年ごとに行われる保険料の見直しが重なって迎える2012年度の介護保険は、利用者も事業者も介護職員にとっても大変厳しい見直しの状況になりました。
介護保険を運営する県内63団体のうち7割以上の団体で保険料を引き上げる。いくつかの団体は月額が5000円を超えると言われています。
○介護保険料の大幅な引き上げで、低階層への保険料負担を軽減するため市町村では多段階に分ける方法や利用料の減免など低所得者層の負担軽減の検討がされています。
さらに、保険料負担の割合が県・市町村はそれぞれ12.5%という割合になっています。この負担割合を超えて保険料の軽減をはかることはできないかという自治体もあるようですが、県としてどう考えるのか。もし、12.5%を超えることが可能であれば、県としても検討できないか。お聞きします。
○昨年の介護保険改定で、2012年度に限り保険料上昇の抑制のために、県に設置している財政安定化基金の一部を取り崩すことが可能といわれています。県として基金の取り崩しによって保険料抑制はどの程度なのかお聞きします。そのさい、保険料が納められない世帯への支援はできないか。あわせて健康福祉部長にお聞きします。
国は保険料が大幅に引きあがることを承知のうえで、本来は国が負担割合を増やして、保険料抑制をすべきところ、今回にかぎり財政安定化基金の取り崩しで抑制するようにとのことではないのでしょうか。県はもっと基金の取り崩しができないか。これ以上の取り崩しができないのであれば、やはり保険料を抑えるために国の負担を増やすよう求めてほしいと思います。再度、健康福祉部長にお聞きします。
介護職員の処遇改善について
介護人材が不足しているということは、昨日の金子議員の質問でもあきらかになりました。きつい仕事の上に、低賃金、訪問介護職員の85%は非常勤職員という状況を改善するために国は年1900億円全額国費で処遇改善交付金を実施してきましたが、来年度は介護職員の処遇改善交付金が廃止されます。
交付金がなくなることで介護報酬が実質マイナス改定になり、事業所の経営を圧迫し、その分、介護職員の給与が賃下げされるのではないかと懸念されています。賃下げなどされないよう引き続き、国に介護職員の処遇改善を求めるべきと思います。いかがですか。
○介護職員によるたんの吸引など医療行為ができるようになるということで、今後はたんの吸引、経管栄養など介護職員による医療行為の拡大がなされるのではないかと現場では不安が広がっています。たんの吸引は現実には介護職員が必要に迫られてやっていたからと、現状を追認し、研修の保障がされているとは思えません。十分な研修の機会を保障することなく、医療行為の拡大にならないよう歯止めをかけるべきではないでしょうか。根本的に解決するのに必要な医師・看護師等医療体制の確保がされるよう対策をすべきと考えます。健康福祉部長にお聞きします。
「介護保険サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の附帯決議では、介護職が喀痰吸引等を実施するにあたっては、知識・技術の十分な習得をはかるとともに、医師、看護師その他の医療関係者との連携のもとに、安全管理体制を整備し、そのうえで実施状況について定期的な検証を行うこと。
とされています。この主旨がきちんと担保されるよう要望します。
「地域包括ケア」への移行について
(2025年、団塊の世代が後期高齢者になられるわけです。ここを見据えて)施設から在宅へと「地域包括ケア」で大きく舵をきる方向が示されました。
地域包括ケアは、住居の種別(従来の施設、有料老人ホーム、グループホーム、高齢者住宅、自宅)にかかわらず、おおむね30分以内に生活上の安全・安心・健康を確保するための多様なサービスを24時間365日利用しながら地域での生活を継続することができる。ことを目指すそうですが、「地域包括ケア」は施設から在宅へという方向が示されたということでしょうか。現実には特養の施設入所を待っておられる方々が在宅で約5200人、他の施設での待機者が約3200人という状況です。今後も特養の施設整備は必要であることは自明のことです。できることなら家に帰りたいといっても、自宅に帰れない、家庭で介護できる状況でない方々が圧倒的です。
特養など入所施設整備は今後どのようになるのか。健康福祉部長にお聞きします。
施設整備が不足しているにもかかわらず、在宅へ方向転換するまでのあいだ、特養入所対象者を、現在は要介護1~5であるが、要介護3~5にせばめる、しぼりこんで当座をしのぐなどということがおこるのではないか、在宅サービスの充実とうたわれていることでさらに施設整備必要数を削減していくのではないかと危惧をいだいている関係者もいます。
在宅サービスの充実がされないまま、入所者の絞り込みで対応することがないように、介護で泣かない長野県が実現できますように。若い部長に大いに期待しております。
2.長野広域のごみ処理について
一般廃棄物の処理が広域処理になり「ごみ処理広域化計画」に県としても深くかかわっている。
○ごみの量は、県民の協力と3Rの推進で総量が減少しています。長野広域でもごみ処理の有料化や分別による資源化の取り組みによって、平成26年度の目標としていた家庭系、事業所系の可燃ごみ減量目標を5年も前倒しで平成21年に達成することができ、今後も人口減少とごみ減量でさらに減量できると思われます。そういう状況でありながら、ごみ処理広域化基本計画の見直しでは、ごみ処理施設規模は前のまま変更されないという問題があります。減量したごみの量に合わせた焼却施設規模に計画の見直しをするよう県は積極的に指導すべきではないかと思いますが、環境部長いかがですか。
○環境省はダイオキシン対策として、平成9年には、ごみ処理広域化、焼却施設の大型化をすすめてきました。同時に、大型焼却炉建設の際は、焼却灰・飛灰の溶融固化施設の設置が原則でありました。しかし、溶融炉建設コストが高い。技術的課題が多い。管理・維持経費がかさむ。大事故が発生したなどの経緯で、焼却施設建設に、溶融固化施設を原則設置から、設置しなくてもよいという見直しがされています。(県としてごみ処理計画に組み込まれている灰溶融固化設備の見直しをするよう周知しているか。)環境省の姿勢が変わっていることもあわせて、計画の見直しができないか。環境部長にお聞きします。
環境の世紀といわれる時代、「大量生産・大量消費・大量廃棄」によってごみが生み出され、出るごみは大型焼却炉によって燃やす、ごみの"焼却中心主義"を見直すことが大事と思います。信州の環境保全、ごみ減量へご苦労ですが、よろしくお願います。
3.TPPについて
高村県議が、TPPに日本が参加した場合の県民に与える影響を県としてどう試算しているかどのように情報収集しておられるか。と質したことに対し、
企画部長は、国や県内の関係団体から情報収集してきた。(14日には国の担当者を招いて説明会を開き、県民に情報提供した。)
国は交渉に向けた事前協議の段階としており、「影響を推し量るうえでの基本的な条件すら見えていない。県内の影響を合理的に試算できる段階にはない。」との答弁はあまりにも無責任(ノーテンキ)、開いた口がふさがりません。
TPP交渉参加国間では、すべての関税が撤廃されるということが前提条件であり、その他に、非関税障壁についても交渉するということです。アメリカ側からは、日本がTPP参加をするのであれば、必要な構造改革をおこない、競争政策、投資、金融サービス、デジタル経済、政府調達、知的財産権、原産地規制のような諸分野での新秩序をつくりだすようにと強く迫られています。
医療、保健、金融、労働力など非関税障壁については、現段階で試算するには困難な面もあると思います。しかし、関税が撤廃されることで生じるメリット・デメリットについては一定の検討・試算ができるのではないですか。
現に、農政部では農業生産額は685億円。平成20年農業産出額の4分の1が落ち込むと試算しています。
かつて、木材の関税が撤廃されたことによって日本の林業が受けた影響など参考にすべきです。木材では残っているのは「合板」だけと関係者からお聞きしました。関税撤廃によって県内林業への影響は試算できるのではないかと思います。林務部長にお聞きします。
逆に、県内製造業で輸出関連企業にとって、現在の取引先国の関税が撤廃されることによるメリットがどの程度あるのでしょうか。メリットは単純にはわからないということであれば、関税によって輸出できないという不利益をこうむっている企業があるのでしょうか。商工労働部長にお聞きします。
農政部は農林水産省の影響試算に基づいて試算し、平成22年12月24日に庁内でおこなわれた「包括的経済連携に関する連絡会議」に資料を提出しています。これは公表され、私たちも資料をいただいています。
新聞報道ですが、今月22日にはTPPをめぐる政府の動向に対応する「国際的な経済連携に関する対策会議(議長は阿部知事)が開かれ、各部が県内の各種団体から聞き取った意見を報告した。
商工労働部は商工団体の意見として「県内の製造業は輸出に依存しており、関税撤廃によるメリットへの期待がある一方、中小企業は競争が激化し、経営が立ち行かなくなる懸念がある」
農政部は農業団体から「関税撤廃で、特に中山間地域の農業衰退が心配」
林務部は林業団体から「木材は既に輸入自由化で関税はゼロ。円高で外材が入手しやすくなり、林業の衰退を招くのではないか」とそれぞれ報告があったと記されています。22日に庁内で対策会議で各部局からの報告を受けているわけであります。
であるにもかかわらず、24日の代表質問の答弁はあまりにも不誠実ではありませんか。
全国的にも、県内でも、TPP交渉に参加しないように求める世論や運動が広がっています。
JAや農業会議など農業関係団体はもとより、医療関係者、県内ではっきり反対の表明をしている町村長もおられます。
JA長野中央会の大槻会長は、しんぶん赤旗のインタビューに答えて、「環太平洋連携協定に参加すれば、国民の命を守る上で、大変な事態を招くことになります。国の形を変えるどころか、この国をつぶしてしまうことになるんじゃないかと危惧しています。」
長野市医師会の新年会では、県医師会長の大西先生が来賓あいさつで、TPPによって国民皆保険制度が危機的になることを訴えておられました。
23日付「信濃毎日新聞」報道では、22日、県世論調査協会の県民意識調査はTPP反対32%、賛成27%と反対が上回りました。そして、TPPの影響や内容について、政府は「あまり説明していない」53%、「まったく説明していない」25%と8割近くの方が政府の説明不足を指摘しています。
同じ世論調査で、長野県に対して67.3%が「もっと県内への影響について情報提供してほしい」と要望しています。
企画部長が担当部長として、情報収集し知事に報告する。そして、知事ははっきりと県民に情報提供する。これが県民が県政に、阿部知事に望んでいることです。
県がきちんと情報や影響を公表し、国にも情報の公開を働きかけるべきだと考えます。企画部長に伺います。
非関税障壁の緩和にむけて、24の作業部会が設けられています。政府は、交渉状況について21分野の状況を報告されたそうです。この報告では、日本政府が懸念を認めた分野は13にも及んでいるということもいわれています。
また、野田総理もISD条項は寡聞(かぶん)にして詳しく知らなかった。と11月15日付「東京」で報じられたように、「投資関連(ISD)条項」が問題になってきています。
事前協議の段階でも、さまざまな問題をTPPは抱えています。
TPPは、国の形を変える重大なことであり、今後の交渉は秘密裡にすすめるということです。
そこまで、危険をおかして参加する必要はないと思います。
知事は、国に言うべきことをはっきりと言っていただきたいと申し上げて私の質問を終わります。
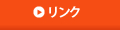

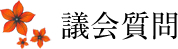 議会質問
議会質問